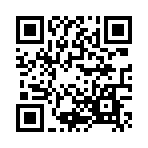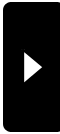雪野山古墳(2)
2015年10月30日
 雪野山古墳を見に行きましょう
雪野山古墳を見に行きましょう
雪野山歴史公園などの山のふもとから、歩いて30~40分で雪野山山頂にあります、雪野山古墳にたどり着きます。
雪野山古墳は発掘調査によって、全長約70mの前方後円墳であったと推定されます。南西側に直径40mの後円部があり、2段に土盛りがされています(後円部二段築成)。後円部の三角点付近に竪穴式石室が見つかっています。発掘調査後は埋め戻され、現在は四角い土段状になっています。この土は旧八日市役所の新人職員が歩荷で運び、石室を養生したとのこと!標高およそ308mとはいえ、今も昔も山頂は大変です!
前方部は長さ約30mで、特に北側裾は自然地形の尾根へと延び、左右対称でないバチ状に開いたような形とみられます。

→平面測量図です。色付けは発掘調査された部分を表しています。
(八日市市教育委員会『雪野山古墳Ⅲ』1993)
→北側の前方部から見た写真です。なんとなく後円部と前方部の形が見えますか?

→東側横からみた現況模式図です(trinetを使用して作成)。
後円部の高さは4.5m、前方部の高さは2.5mが残っていました。この現況図はさらに10m程度下まで測量していますので、古墳は上の部分だけです。周辺は急傾斜で、後世の開削や土崩れもあったと思われますが、山頂に古墳をつくることによって、規模がより大きく見えるということもあったかもしれません。
 古墳にはあちこちになにやら石が…雪野山は湖東流紋岩と呼ばれる石の山で、山中には巨石も多くあります。雪野山古墳はこの石で表面に葺石を施したり、岩盤を利用し、古墳を形作っていました。竪穴式石室も湖東流紋岩です。
古墳にはあちこちになにやら石が…雪野山は湖東流紋岩と呼ばれる石の山で、山中には巨石も多くあります。雪野山古墳はこの石で表面に葺石を施したり、岩盤を利用し、古墳を形作っていました。竪穴式石室も湖東流紋岩です。
→横穴式石室の痕跡と見られます。雪野山古墳より後の時代に作られた後期古墳で、雪野山中には横穴式石室が露出しているところがたくさんあります。
→ほこら跡で、階段状に並べています。後世に雪野山古墳の石室の天井石を利用した?ともいわれています。探訪の際は動かさないようにお願いいたします。
→石垣です。後世に山城として使われた痕跡とみられます。また前方部に竪堀状に削られた跡もあります。 雪野山の近くに後藤館遺跡があり、佐々木六角氏の家臣であった後藤氏の館跡とされます。雪野山古墳を加工して作られた城は、この後藤氏の城ではないかと考えられています。
1700年前の王さまがもっていたピカピカ の鏡をつくってみよう!
「あかね古墳公園」で古墳の説明を。
「雪野山の古墳をめぐろう」を開催しました。
11月10日(日)「雪野山の古墳をめぐろう」開催します!
あかね古墳公園で「蒲生野夢あかり」が開催されました。