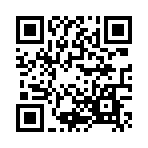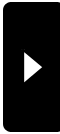盆踊りの季節です
2016年07月14日

 東近江市では、盆踊りといえば「江州音頭」です
東近江市では、盆踊りといえば「江州音頭」です

江州音頭は、幕末のころ、祭文語りの名人、桜川雛山に弟子入りした初代桜川大竜(西澤寅吉)が、雛山から習った祭文に、念仏踊りや歌念仏を取り入れ、音頭に仕立てたものを「江州八日市祭文音頭」といい、真鍮屋好文の協力を得て、やがて「江州音頭」として大成したといわれます。
踊りを伴う「棚音頭」とともに、踊りを伴わない音頭を読み上げる「座敷音頭」も盛んに行われています。
江州音頭は、近江商人兼音頭取りの出稼ぎ先で昭和初年から盛んに行われ、大阪千日前でも人気を博したとされます。上方漫才界で有名な砂川捨丸は、もともと江州音頭の音頭取りであったことから、江州音頭が漫才のルーツ
 ともいえそうです。
ともいえそうです。また、テイチクレコードやコロンビアレコードで発売された江州音頭のレコードも、普及に貢献したと考えられます。
八日市で歌寅らによって創始されたという意味で、八日市が江州音頭発祥の地といわれます。金念寺(金屋町)境内には、江州音頭家元の「桜川大竜」墓が明治25年に門弟により建立されており、また同寺には「桜川寿賀山記念碑」、「真鍮屋之碑」も建立されています。

 昭和40年代になって保存運動が活発化し、旧八日市市内では、江州音頭の保存と踊りの普及などを目的に、、「江州音頭保存会」が昭和40年に設立されました。
昭和40年代になって保存運動が活発化し、旧八日市市内では、江州音頭の保存と踊りの普及などを目的に、、「江州音頭保存会」が昭和40年に設立されました。昭和44年、八日市駅前の延命公園に「江州音頭発祥の地」記念碑が建立され、昭和46年には、旧八日市市(現東近江市)無形民俗文化財「江州音頭」(保護団体:江州音頭保存会)に指定されています。
昭和45年からは、八日市商工会により金念寺周辺の金屋大通りを中心とした聖徳まつり市民総踊りがはじまり、現在は八日市駅前に場所を移して、江州音頭発祥の地にふさわしく盛大に行われています。
浴衣の新調

平成23年に弘誓寺(五個荘金堂町)で行われた、伝建協大会での民俗芸能鑑賞。見ているだけでは済みません

全員スタンドアップ



踊りが盛り上がれば、音頭取りさんも調子が上がり、エンドレス状態に

 江州音頭は娯楽でもありますが、芸能文化としての重要性からも今後の継承を危惧され、子どもたちに講座をおこなうなど後継者作りに尽力されておられる、市内在住の座敷音頭の二代目家元桜川昇龍氏、棚音頭の三代目家元真鍮家好文氏の両氏が、平成24年度に市指定無形文化財となっています。
江州音頭は娯楽でもありますが、芸能文化としての重要性からも今後の継承を危惧され、子どもたちに講座をおこなうなど後継者作りに尽力されておられる、市内在住の座敷音頭の二代目家元桜川昇龍氏、棚音頭の三代目家元真鍮家好文氏の両氏が、平成24年度に市指定無形文化財となっています。
流派は異なりますが、江州音頭を残したいという思いで行われた共演会は、感動でした

 東近江市文化遺産活用活性化実行委員会による、
東近江市文化遺産活用活性化実行委員会による、平成24年度江州音頭歴史的音源保存事業 「村井市郎音頭資料コレクション (江州音頭編)」 CDは、
音頭研究家村井市郎氏(故人)が長年にわたり蒐集された音頭資料のうち、ご家族のご厚意により提供いただいた江州音頭SPレコードの音源をデジタル化保存したものです。
市内図書館などで貸し出しされていますので、ぜひ聞いてみてくださいね

 江州音頭については、『八日市市史 第三巻 近代』をご参考になさってください
江州音頭については、『八日市市史 第三巻 近代』をご参考になさってください
明日、「近江の聖徳太子 その魅力を語る」開催!
木地師資料の調査ボランティアスタッフ募集!
川合東出の石棺仏
近江商人屋敷「旧中江勝治郎邸」特別公開!
近江の聖徳太子1400年プレイベント「舞楽奉納」がありました
「聖徳太子の文化サポーター養成講座」の参加者募集中!
木地師資料の調査ボランティアスタッフ募集!
川合東出の石棺仏
近江商人屋敷「旧中江勝治郎邸」特別公開!
近江の聖徳太子1400年プレイベント「舞楽奉納」がありました
「聖徳太子の文化サポーター養成講座」の参加者募集中!
Posted by 東近江市埋蔵文化財センター at 09:00
│民俗