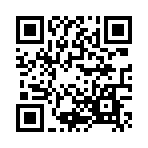夏休みまいぶん体験教室を開催しました
2016年07月29日
 平成28年7月29日(金)、埋蔵文化財センターで、午前中に土偶消しゴムつくり、午後に勾玉つくりを行いました
平成28年7月29日(金)、埋蔵文化財センターで、午前中に土偶消しゴムつくり、午後に勾玉つくりを行いました
小学校1年生から6年生まで、各回20名が定員でしたが、申込開始からすぐに満席になってしまい、お断りさせていただいた方もおられました。大変申し訳ございませんでした。
 土偶消しゴムつくりは、相谷熊原遺跡出土の土偶にちなんで実施しました。
土偶消しゴムつくりは、相谷熊原遺跡出土の土偶にちなんで実施しました。施設見学の中では、先だって作成した土偶精密レプリカを公開しました。
センター1階の展示コーナーの様子です。
参加の皆さんが好きな形に造形し、土偶をつくった昔の人々のことを思い・・・
展示やリーフレットに掲載されている考古遺物を再現、考古ボーイの作品です

土偶以外にも色々なものに興味を持ってもらったようで、うれしい限りです。
 勾玉つくりは、やわらかい滑石をつかってつくりました。
勾玉つくりは、やわらかい滑石をつかってつくりました。勾玉の説明の様子です。神妙な面持ちで聞いていました。
勾玉磨きの様子、納得のいくまで磨きました。
完成した勾玉です。とんがりの部分を特に念入りに

火起こし体験もしましたよ!
これをきっかけとして、また埋蔵文化財センターへ見学や調べものに来てくださいね!
八日市飛行場
2016年07月22日
 旧陸軍八日市飛行場跡についてご紹介します。
旧陸軍八日市飛行場跡についてご紹介します。
八日市飛行場は、東近江市の沖野ヶ原と呼ばれる一帯に、大正4年頃に国内初の民間飛行場として設立されました。その後、運用の面から陸軍誘致に乗り出し、大正11年頃に国内3番目の陸軍飛行場となり、先の戦争まで使用されました。
飛行場ができた理由として、沖野ヶ原は1万年以上前の愛知川の氾濫原で水はけがよく、地形が平らで、風を受けやすく、江戸時代から大凧まつりが行われるような場所であることが挙げられます。また、国内で飛行機が入ってきたばかりの頃で、先鞭をつけようと地域の人々が私財を投じて誘致運動を起こして成功しました。現代につながる、新たなまちづくりがはじまったのです。
飛行場を中心として、軍関係施設が作られ、湖南鉄道(→八日市鉄道→近江鉄道)飛行場線が敷かれます。また、現在の東近江総合医療センターは、元は陸軍病院でした。現在の工場や道路は飛行場の施設の敷地を利用し、その地形は地図などから確認できます。

 飛行場は度々拡張され、最終的には南側の蛇砂川まで広がりました。
飛行場は度々拡張され、最終的には南側の蛇砂川まで広がりました。
 東近江市立八日市文芸会館前(青葉町)に設置されている「民間飛行場発祥地」碑
東近江市立八日市文芸会館前(青葉町)に設置されている「民間飛行場発祥地」碑
 陸軍飛行第三聯隊跡碑(札の辻の日産の角です)
陸軍飛行第三聯隊跡碑(札の辻の日産の角です)
 飛行第三聯隊正門跡碑(札の辻のローソンの角です)
飛行第三聯隊正門跡碑(札の辻のローソンの角です)
 冲原(おきはら)神社は、陸軍飛行場となった大正14年に衛戍神社として創祀、昭和2年に冲原神社に改名されました。地元の皆さんによって美しく整えられています。
冲原(おきはら)神社は、陸軍飛行場となった大正14年に衛戍神社として創祀、昭和2年に冲原神社に改名されました。地元の皆さんによって美しく整えられています。
 冲原神社には、発掘されて見つかった飛行場の営門が移築されています。
冲原神社には、発掘されて見つかった飛行場の営門が移築されています。
軍建物は戦後、学校などに転用されましたが、老朽化により維持が難しく、その姿を消しています。
 八風街道の北側へ1本入った道は、鉄道の敷地の痕跡と見られます。
八風街道の北側へ1本入った道は、鉄道の敷地の痕跡と見られます。

 八日市飛行場の周辺には、昭和19年頃、飛行機などを隠すための掩体壕が作られました。現在は、布引丘陵沿いに残るのみで、埋蔵文化財包蔵地としては「布引掩体群」と名称つけています。遊歩道沿いに、コンクリート造ドーム型掩体や木製ドームを支えたコンクリート基礎など、17基が残ります。戦後、陸軍からそのまま土地所有者へ返還され、個人では解体できずに残ったものです。
八日市飛行場の周辺には、昭和19年頃、飛行機などを隠すための掩体壕が作られました。現在は、布引丘陵沿いに残るのみで、埋蔵文化財包蔵地としては「布引掩体群」と名称つけています。遊歩道沿いに、コンクリート造ドーム型掩体や木製ドームを支えたコンクリート基礎など、17基が残ります。戦後、陸軍からそのまま土地所有者へ返還され、個人では解体できずに残ったものです。
 戦後の復興により、今では飛行場があったということはなかなか想像できません。戦争を知る方々が少なくなる中、いわゆる戦争遺跡は、その記憶を目の当たりにできる大きな役割を果たし、その重要性は益々高くなっていくと思います。
戦後の復興により、今では飛行場があったということはなかなか想像できません。戦争を知る方々が少なくなる中、いわゆる戦争遺跡は、その記憶を目の当たりにできる大きな役割を果たし、その重要性は益々高くなっていくと思います。
八日市飛行場については、『八日市市史 第4巻 近現代』編をご参照ください
盆踊りの季節です
2016年07月14日

 東近江市では、盆踊りといえば「江州音頭」です
東近江市では、盆踊りといえば「江州音頭」です

江州音頭は、幕末のころ、祭文語りの名人、桜川雛山に弟子入りした初代桜川大竜(西澤寅吉)が、雛山から習った祭文に、念仏踊りや歌念仏を取り入れ、音頭に仕立てたものを「江州八日市祭文音頭」といい、真鍮屋好文の協力を得て、やがて「江州音頭」として大成したといわれます。
踊りを伴う「棚音頭」とともに、踊りを伴わない音頭を読み上げる「座敷音頭」も盛んに行われています。
江州音頭は、近江商人兼音頭取りの出稼ぎ先で昭和初年から盛んに行われ、大阪千日前でも人気を博したとされます。上方漫才界で有名な砂川捨丸は、もともと江州音頭の音頭取りであったことから、江州音頭が漫才のルーツ
 ともいえそうです。
ともいえそうです。また、テイチクレコードやコロンビアレコードで発売された江州音頭のレコードも、普及に貢献したと考えられます。
八日市で歌寅らによって創始されたという意味で、八日市が江州音頭発祥の地といわれます。金念寺(金屋町)境内には、江州音頭家元の「桜川大竜」墓が明治25年に門弟により建立されており、また同寺には「桜川寿賀山記念碑」、「真鍮屋之碑」も建立されています。

 昭和40年代になって保存運動が活発化し、旧八日市市内では、江州音頭の保存と踊りの普及などを目的に、、「江州音頭保存会」が昭和40年に設立されました。
昭和40年代になって保存運動が活発化し、旧八日市市内では、江州音頭の保存と踊りの普及などを目的に、、「江州音頭保存会」が昭和40年に設立されました。昭和44年、八日市駅前の延命公園に「江州音頭発祥の地」記念碑が建立され、昭和46年には、旧八日市市(現東近江市)無形民俗文化財「江州音頭」(保護団体:江州音頭保存会)に指定されています。
昭和45年からは、八日市商工会により金念寺周辺の金屋大通りを中心とした聖徳まつり市民総踊りがはじまり、現在は八日市駅前に場所を移して、江州音頭発祥の地にふさわしく盛大に行われています。
浴衣の新調

平成23年に弘誓寺(五個荘金堂町)で行われた、伝建協大会での民俗芸能鑑賞。見ているだけでは済みません

全員スタンドアップ



踊りが盛り上がれば、音頭取りさんも調子が上がり、エンドレス状態に

 江州音頭は娯楽でもありますが、芸能文化としての重要性からも今後の継承を危惧され、子どもたちに講座をおこなうなど後継者作りに尽力されておられる、市内在住の座敷音頭の二代目家元桜川昇龍氏、棚音頭の三代目家元真鍮家好文氏の両氏が、平成24年度に市指定無形文化財となっています。
江州音頭は娯楽でもありますが、芸能文化としての重要性からも今後の継承を危惧され、子どもたちに講座をおこなうなど後継者作りに尽力されておられる、市内在住の座敷音頭の二代目家元桜川昇龍氏、棚音頭の三代目家元真鍮家好文氏の両氏が、平成24年度に市指定無形文化財となっています。
流派は異なりますが、江州音頭を残したいという思いで行われた共演会は、感動でした

 東近江市文化遺産活用活性化実行委員会による、
東近江市文化遺産活用活性化実行委員会による、平成24年度江州音頭歴史的音源保存事業 「村井市郎音頭資料コレクション (江州音頭編)」 CDは、
音頭研究家村井市郎氏(故人)が長年にわたり蒐集された音頭資料のうち、ご家族のご厚意により提供いただいた江州音頭SPレコードの音源をデジタル化保存したものです。
市内図書館などで貸し出しされていますので、ぜひ聞いてみてくださいね

 江州音頭については、『八日市市史 第三巻 近代』をご参考になさってください
江州音頭については、『八日市市史 第三巻 近代』をご参考になさってください
【情報提供】東近江の行事・夏
2016年07月11日
 平成28年7月17日(日)13:00~15:30
平成28年7月17日(日)13:00~15:30五個荘コミュニティーセンター第17回歴史公開講座
「開館20周年を迎える観峰館と竜田町についての講演会」
場所:五個荘コミュニティーセンター
〒529-1422 東近江市五個荘小幡町318
電話0748-48-2837
 平成28年7月18日(祝)10:30~15:00
平成28年7月18日(祝)10:30~15:00第24回 惟高親王祭(これたかしんのうさい)
第1部:例祭、語り芝居(木地山真美さん)
第2部:講演会
筒井正さん「木地師を育んだ小椋谷の自然の暮らし」
山崎享さん「つながりが支えるアジアの猛禽類と生態系」
主催:蛭谷自治会・惟高親王祖神講本部
場所:第1部・筒井八幡(筒井御陵・惟高親王像のある峠の手前)
第2部・木地師やまの子の家
永源寺エリア探訪マップ(東近江市観光協会)をご参照ください
 平成28年7月23日(土)19:00~
平成28年7月23日(土)19:00~第47回 八日市聖徳まつり(江州音頭総踊り・フィナーレ花火)
場所:八日市駅前大通り
主催:八日市聖徳まつり実行委員会
問合:八日市商工会議所(電話0748-22-0186)
 平成28年7月31日(日)12:00~
平成28年7月31日(日)12:00~第14回 雪野山歴史まつり
柴田勝家が陣を張った甕割山にちなんだ水鉄砲合戦、子どもの広場や屋台がたくさん出店されています。
雪野山山頂も、古墳が築かれたのちに中世山城に改築されていて、近くには中世城館跡の後藤館遺跡もありますので、合戦とのかかわりは雪野山にもありますよ

場所:雪野山歴史公園(東近江市上羽田町)
主催:雪野山歴史まつり実行委員会
問合:平田コミュニティーセンター内「ひらた夢回議」事務所
hirata-co @e-omi.ne.jp(@の前は詰めてください)
※水鉄砲合戦募集7/15まで 申込様式等詳しくは市ホームページ
昨年のステージ周囲に「雪野山古墳」幟を立てさせていただきました。